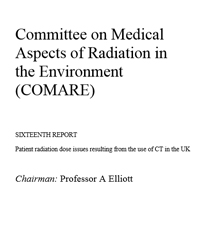|
(2015.4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No.060-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
放射線被曝に安全量はない -There is no safe dose of radiation その⑤低線量内部被曝の危険は実は“非がん性疾患”にある(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (この記事は、第124回広島2人デモチラシ<2015年3月6日>を下敷きにしている。チラシに引きずられて、口調も「だ、である調」から「です、ます調」に改める。また通常記事では、敬称は一切省いているが、この記事では敬称をつけることにした) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズも5回目になってこう言い出すのも気が引けますが、図1は放射線被曝理解のための概念フローチャートです。もう少しいえば、低線量内部被曝を理解するための概念フローチャートです。 『放射線被曝に安全量はない』という言葉を出発点にして、私が理解した道筋をたどったフローといってもいいかもしれません。 といって文字通りこの順番で理解していった訳ではなく、この順番で理解すればよかったかな、と考えているフローです。 若干説明します。 “低線量内部被曝”を理解するためには、膨大な裾野の広い関連した分野の知識と知見、それにものごとをしっかり見据える視点が必要です。こうした場合、通常、まず専門家のいうところを聞いて、専門家の指し示す道筋をたどって学習し、理解と知見を深め、従って知識もさらに広がる・・・というパターンが用意されているのですが、こと、放射線医学や被曝問題に関する限り、このパターンが全く通用しません。専門家が信頼できないのです。最初から、頭から信用しないというのではなく、まず専門家の言説に、前後相矛盾が多い、自家撞着がしばしば見られる、という点に疑問を感じるからです。 典型的には、「放射線被曝に安全量はない」といいながら、「100ミリシーベルト以下では健康影響はない」とする点でしょう。健康影響がないのなら、100ミリシーベルトは「安全」の「閾値」はずです。ところが、100ミリシーベルトは安全値ではない、閾値ではない、という、直感的に、これは学問体系のどこかがおかしい、欠陥がある。と感じるわけです。 そうして調べていって見ると、専門家たちが、放射能、特に人工放射能と私たちの生活空間とが共存できる社会を合理化する理論構築に、その全精力を費やしていることが次第にわかってくる、これは、エセ学問、エセ科学だな、という感じがだんだん強くなっていきます。 歴史的に見て、当時当代の専門家たちが、当時当代の権力や特定利益グループのみに奉仕する学問体系や理論体系を構築する、というケースは何も珍しいことではなく、非常にしばしば発生していることです。もしかすると、放射線や被曝に関する専門家たちもそうした事例の一コマかもしれない、とあたりがだんだんついてきます。もちろん中川保雄の『放射線被曝の歴史』とか、欧州放射線リスク委員会(ECRR)2010年勧告とか、一連の優れた著作や報告などの助けを借りなければ、こうした認識になかなか到達しえません。私の場合は、「日本に対する原爆使用」問題とそれを契機に立て続けに発生する一連の諸事件に関する勉強も大いに役立っていたのかもしれません。 さてこうしてあたりがついてくると、どうしても道筋をつける、といった本来専門家の仕事を、自分自身でやらなくてはならなくなります。ですから、図1で示したフローなどが大いに役立ってくることになります。
私の場合、出発点は『放射線被曝に安全量はない』でした。そうすると放射能とはいったい何か、という根本問題に立ち返って理解をすすめる必要がありました。すると放射能とは、電離放射線の、細胞を構成する分子や原子に対する電離化作用(イオン化作用)のことだとわかります。ここで重要な区別が見えてきます。すなわち―。
この理解がしっかり自分の中で確立すると、たとえば、文部科学省の「放射線副読本」のように、わざと電離放射線と非電離放射線を混同させるような説明にも戸惑わなくなります。あるいは「電離放射線も危険だが、非電離放射線も危険だ」といった言説にも惑わされなくなります。 つまり「非電離放射線が危険という言説があるが、非電離放射線が危険かどうかさておいて、今は電離放射線の特質である放射能について考察している。非電離放射線の話は、今は横に置いておこう」という風に。 次に「人間はなぜ放射能に弱いのか」という問題を立てて調べていくと、「人間はなぜ放射能に弱いのか」という問題の立て方そのものが誤りであることがわかってきます。すなわち、地球46億年の歴史の中で、地球表面に放射能の危険がほぼなくなり、地表が2重のシールドで防御されることを絶対条件として、人類が生まれ進化してきたのだ、ということがわかってきます。 放射能に弱いのではなく、放射能の影響のないことが人間の生存の条件なのだ、という理解に達します。すなわち-。
という理解に達します。この科学的真理に対する理解は、「人類と放射能を共存」させようとする、国際的な核利用推進勢力、とくに国際放射線防護委員会(ICRP)の言説は、一挙に何かしらいかがわしい、なにか別な目的をもった学説と見えてきます。 次に、自然放射線(自然放射能)と人工放射線(人工放射能)の違いの理解へと進みます。前述のように、自然放射線は、地球46億年の歴史の中で、強烈な放射線だらけの宇宙空間に比べれば、地表面ではなきに等しい状況となりました。それを前提条件として人類が生存し続けていることを考えれば、普通に暮らす私たちにとって、生存を脅かしているのは人工放射線だと理解されます。 さらに、人間活動が、本来地中深くで眠るべき危険な放射性物質を、地表面の生活空間に引きずりだしました。(人造放射能)私たちに災いをなすのは、こうした人工放射能や人造放射能なのだとわかります。すなわち-。
次に、放射線被曝そのものを、根幹から理解する必要に迫られます。本質的に放射線被曝とは、細胞の生きる力を奪うことであり、自然によらない人工的に細胞の老化を促進すること(不特異老化)なのだと理解が進みます。しかも細胞に関する科学、分子・細胞学が発展するに従って、単純にDNAが切断されるなどといった被曝損傷パターンだけではなしに、様々な被曝損傷タイプがあることもわかってきました。すなわち-。
被曝の理解が進めば、外部被曝と内部被曝は全く違う種類の被曝形態であり、外部被曝に比較して内部被曝は、複雑でダイナミックな細胞の活動と密接に絡まり合った、危険なタイプの被曝形態であることに理解が行き着きます。また『放射線被曝に安全量はない』とは、外部被曝よりも内部被曝により当てはまる真理であることも理解されます。内部被曝ではどんなに低線量でも、そのもたらす健康損傷はきわめて大きい、場合によれば、同じ線量でも外部被曝に比べ内部被曝は1000倍から2000倍のオーダーで危険です。すなわち-。
という結論が得られるのです。 ところで、前回まで見たように、ICRP学説信奉者は、実に理屈に合わない、非論理的・非科学的主張を行います。すなわち―。
この主張くらい非論理的な主張もありません。というのは、ICRP学説信奉者は、「放射線被曝に安全量はない」と主張しながら、しかし、「100mSv以下での低線量被曝では、健康に害があるという科学的証拠はない」とも主張しています。それでは、低線量被曝で、健康に害があるという科学的証拠が出てこなかったのかというとそうではなく、その肝心な部分はほぼ無視したままで、「100mSv以下の世界では、わからないことが多い」と率直に吐露します。つまり「科学的証拠がない」という言い方も実はミスリードな言い方で、「100mSv以下はわからない」とするのが正直なところです。 これは、ICRP学説信奉者の採用してきた研究手法がもうすでに限界に達しているということでもあります。すなわち、疫学(一種の統計学)の手法では、低線量被曝、特に低線量内部被曝の世界は科学的に解明できない、ということでもあります。低線量内部被曝の世界は、疫学的手法を使いながらも、もっと分子・細胞生物学的手法を使わなければ解明できないのです。 ここまでは、ICRP学説信奉者に限らず、すべての医科学者にとっては共通認識化しているといってもいいでしょう。 ところがICRP学説信奉者は、低線量被曝の健康影響についてはわからない、といいながら、その健康影響は“がん”と白血病だけだ、と主張するのです。これが主張できるのは、低線量被曝の影響が解明できた時にはじめて、“科学的真理”として主張できるのであって、“わからない”といいながら、その健康影響は“がん”と白血病だけだ、と主張するのは典型的な自家撞着でしょう。ここがICRP学説の胡散臭いところです。
“がん”とは細胞の暴走状態のことです。本来寿命を終えて死滅すべき細胞(テロメアの寿命)が、死滅せず無限に異常増殖していくことです。多細胞生物の体を構成する細胞は、まことにうまくできていて、寿命を迎えた細胞は死滅するようにプログラムされています。(アポトーシス=管理・調節された細胞の自殺)電離放射線が細胞に作用して(特に遺伝情報=ゲノムに)、細胞がアポトーシスを迎えずに暴走し、がん化することは、大いにあり得ることです。が、それにしても“がん”は放射線被曝症状のひとつにすぎません。放射線被曝の原理やメカニズムの理解が深まるにつれ、低線量被曝の症状は、ほぼ“がん”と白血病であるとするICRP学説はますますおよそありそうにない、信じがたい説だということになります。 ICRP学説が、低線量被曝の健康影響(放射線の確率的影響)は致死性“がん”と白血病だけだとする根拠はいったい何か、という点については、このシリーズの最後半で、『ICRPとは何か』という表題のもとに扱うことにします。ここでは、低線量被曝の健康影響は、“がん”や白血病よりもむしろ“非がん性疾患”の方が、重篤な被害を与えていることを見ておきましょう。 1986年のチェルノブイリ原発事故は、実におびただしい量の、低線量放射線被曝研究をもたらしました。これらは多かれ少なかれ、また意図するしないとにかかわらず、ICRP学説を批判することになりました。 しかし、各国政府の中枢にデンと陣取る“原発推進勢力”と強力にタイアップする国際放射線防護委員会(ICRP)とその学説、及びその学説に基づく“放射線防護政策”の牙城はなかなか崩せませんでした。 一つには各国政治権力を握り、アカデミックな権威を掌中に収めるICRP学説は、これら批判にいちいち反論する必要を認めなかったことが上げられます。下手に反論すると、ボロが出る、ということでもあります。批判に対しては無視という態度をとり続けられるということです。また彼らが権力と権威を背景にする限り、それが可能でした。平たくいうと“金持ち喧嘩せず”となりましょうか。
ECRR2010年勧告第11章『被曝に伴う“がん”のリスク 第2部:最近の証拠』の冒頭から引用します。
断っておきますが、これら諸地域で、目立った核事故を起こしたのは、イギリスのウィンズケール核施設(現在は“セラフィールド”と名前を変えざるをえませんでした)などだけで、後は通常運転中に環境に大量に放射能を放出していた、あるいは現在も放出している地域です。 セラフィールド核施設と類似した白血病発生群が見られる、と指摘されたスコットランドのドーンレイと北部フランスのラ・アーグ再処理工場は桁違いに環境に放射性物質を放出していることでも知られています。特に使用済み核燃料の再処理を行っているアレヴァ社傘下のラ・アーグ再処理施設からは、トリチウムだけで年間1京Bqを越える放射性物質を環境に放出しています。これで、周辺に健康被害が起こらない方がどうかしています。 またスコットランドのドーンレイ核施設については、日本語ウィキペディア『ドーンレイ』が優れた記事を掲載していますので、少々長くなりますが、抜粋引用しておきます。
ドーンレイ核施設には、イギリス原子力公社が材料試験炉や実験炉(冷却材はナトリウム合金)を設置した後、高速増殖炉の原型炉の発電を1975年に開始しましたが、オーストラリアやカナダに新たに有望なウラン鉱山が開発されると、増殖炉の経済性は薄れ、廃炉とすることを決め、1994年に運転を停止、イギリス政府は正式に高速増殖炉計画から撤退しました。一方核燃料再処理施設は1980年から本格操業を開始しましたが、1996年9月の漏洩事故発生で運転停止、すぐに廃止措置が決定されました。 海軍原子力潜水艦用原子炉試験施設は、ドーンレイ核施設敷地内に設けられ、現在第5世代原子炉開発が行われていますが、それも今年2015年には縮小または廃止の方向が決められています。 重要なのは次の記述です。
ドーンレイ地域は、こうして常時放射能汚染地区となった、といっても過言ではありません。 さて、話をECRR2010年勧告に戻します。引用箇所で「これまで研究されてきた核施設を表で示す」と結んでいますが、それが表1です。  ECRRはこれら研究の検討から、リスクはICRPモデルの最大1000倍と結論していますが、現実には、これら地域の有意な“がん”や白血病発症は、ICRP学説が適用されて、放出放射能との因果関係はないとされています。(ただしドイツの原発に関してはドイツ連邦政府が、2000年代に入って大がかりな国家的調査研究=KiKK研究=を全ての原発周辺に関して実施し、“小児性がん”発症との因果関係があるとの結論を出しています) この表でしばしば登場する「COMARE」(コマレ、と発音されているようです)とはどんな組織なのでしょうか? ウィンズケール(セラフィールド)核施設事故などによる低線量被曝の影響が明らかになるにつれて、新たに低線量放射線の影響を全く独立した立場から調査して政府にアドバイスしようという提案がなされ、保健省(Department of Health)の中に、『環境における放射線の医学的様相に関する委員会(Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment=COMARE)』が設立されました。1985年11月のことです。保健省傘下の委員会とはいえ、全く独立した諮問委委員会であることを特徴とします。
話は変わりますが、福島原発事故後の日本においても、このような独立委員会が必要だと私は思います。現在その役割を果たすべきなのは、あえて言えば放射線審議会でしょうが、放射線審議会は、事故後、文部科学大臣の諮問機関から、原子力規制委員会の傘下に入ったとはいえ、そのメンバーはすべてもっとも強硬なICRP学説信奉者によってしめられています。その他に放射線審議会は答申に答える受動的な姿勢、また直接には調査研究を指揮しない、などCOMAREに比較すると、いかにも消極的、受動的存在です。 疑問が出されれば、積極的に能動的に、国家予算を使って調査する、そうした委員会の存在なしには、「フクシマ放射能危機」は乗り切れない、私はそう考えます。 ややCOMAREについて深入りしたかもしれませんが、ヨーロッパにおいては、すでにICRP一色の状況ではなくなっている、ICRP学説に批判的な勢力が一定の影響力と社会的発言力を強めつつあることを見ておきたかったのです。ここが政府・学術界・マスコミ界あげて、ICRP学説一色に塗りつぶされている日本と大きく違うところです。 しかし、全体としていえば、先進各国において、また核兵器保有国であるロシアと中国において、ICRP学説は圧倒的に権力と権威を保持しており、ECRR派などICRP学説に批判的な、あるいはICRP学説と相反・矛盾する調査や研究は無視してきました。あるいはCOMAREのある委員会報告のように、ICRP学説に反する少数意見は、あえて報告本編から削除するなどといった手段も使いました。公式の記録から一切排除することによって、そのような研究や報告は、一切“なかった”ことにするのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||